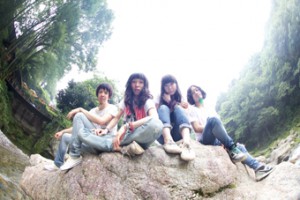 奇跡のアンサンブルを実現したアルバム『CULT POP JAPAN』でデビューし、様々な苦悩と葛藤の末に完成させたミニアルバム『W』では新たな側面を見事に表現したWienners。超絶とも呼べるライブとストイックに突き詰めるソングライティングセンスを誇るシーンのポップアイコンが、その表現の幅を大きく拡げ、個性をより色濃く出した2ndアルバム『UTOPIA』を完成させた。今作で開花したバンドとしての才能は、9月から始まる全国ツアーで見事な桃源郷を描き出すだろう。
奇跡のアンサンブルを実現したアルバム『CULT POP JAPAN』でデビューし、様々な苦悩と葛藤の末に完成させたミニアルバム『W』では新たな側面を見事に表現したWienners。超絶とも呼べるライブとストイックに突き詰めるソングライティングセンスを誇るシーンのポップアイコンが、その表現の幅を大きく拡げ、個性をより色濃く出した2ndアルバム『UTOPIA』を完成させた。今作で開花したバンドとしての才能は、9月から始まる全国ツアーで見事な桃源郷を描き出すだろう。
●2010年7月にリリースしたアルバム『CULT POP JAPAN』は当時の玉屋さんの価値観を詰め込んで、おもちゃ箱をひっくり返したようなポップなファストコア的アルバムでしたよね。
玉屋:はい。
●そして2011年10月にリリースしたミニアルバム『W』は、玉屋さんが音楽を見つめなおしたタイミングで。しばらく曲が書けなくなったとおっしゃっていましたが、いろんな試行錯誤を経て、ポップなファストコアに“メロディ”の概念が入った作品となって。その『W』をリリースしてツアーをし、それ以降というのはどういう流れだったんですか?
玉屋:『W』のときに、“曲が書けない”っていう状態からやっと書けるようになったんですけど、それは聴いてもらっている人だったりとか友達に助けてもらって立ち直ったからなんです。それこそ、『W』に収録した「午前6時」みたいな曲は自分で作ることができるとは思わなかったんですよ。普通に自分の気持ちを歌うという。
●はい。
玉屋:あの曲をライブで改めて歌ったときに“ああ〜、歌を歌うっていうのはこういう感覚なんだ”って初めて思ったんです。“本当にちゃんと歌を聴いてくれてるんだ”って。ライブでやったときの空間のギュッという引き締まり方が、今まで経験したものとはまったく別のものだったというか。
●へぇ〜。
玉屋:今までは“理由はわからないけど熱くなっちゃう”という、音楽の根本的なところを突き詰めていたんですけど、それとは対極にあるかもしれない“気持ちを聴いてほしい”とか“想いを目の前の人に伝える”ということを「午前6時」で初めてやったときに、“歌う”ということの意味に気づいたんです。今までは100人いたとしたら100対1の感覚だったんですけど、今度は1対1が100パターンある、みたいな。だから「午前6時」みたいな曲を作ったということよりも、作って歌って聴いてもらったということを身をもって経験したことが大きかったです。
●ああ〜、なるほど。
玉屋:それで精神的な部分で開放されたというか、当たり前のことだけど気づかなかったことだとかが色々と見えてきて、更に自分の可能性とかバンドの可能性が色んな所に見つかったんです。解き放たれたというか。昨年の年末くらいから『UTOPIA』の制作に入ったんですけど、曲はバンバンできたんですよ。“何をやってもいいんだ”と思えたことで道具がめちゃくちゃ増えたから、いくらでも曲を作ることができるというか。曲の作り方の自分なりのコツをやっと掴んだというか。
●そういった経緯で生まれた2ndアルバム『UTOPIA』ですが、作品として“生”のエネルギーに満ちあふれている印象があって。ネガティブ発信の視点もありますけど、総じて“前に進むための音楽”という。
玉屋:そうですね。それはめちゃくちゃ意識したわけではなかったんですけど、改めて“作品を作る”ということを見つめなおしたときに、自分ができることだとか、自分の得意分野だったりとかを考えたんです。俺はそもそもあっけらかんとしたタイプというか、シリアスなものをシリアスなまま突き付けるんじゃなくて、ユーモアを交えて伝えたり、相手の足元を掬ってハッとさせるというのが自分の強みだと思うので、それはこれからも変わらないだろうし、今作の制作で改めて“俺はこういう人間なんだな”と気づきましたね。
●確かにそういう曲ばかりですね。今作は12曲入りですけど、候補曲はどれくらい作っていたんですか?
玉屋:去年の年末くらいから曲を作り始めたんですけど、1月終わりくらいには候補の11〜12曲くらいは揃っていたんです。
●はい。
玉屋:だから2月に入ってレコーディングを始めるくらいの時期にはアルバムの全体像まで描いていたんですよ。『W』というミニアルバムはWiennersの二面性というか、“静”と“動”の部分があって、それがまだまとめきれないから、まとめないままで出して、次の作品で完結させようと思っていて。だから『UTOPIA』の制作に入った頃は、『W』の延長線上で“静”と“動”の2つの側面を1つにまとめようとしていたんです。
●なるほど。
玉屋:でも、レコーディングと並行してバンドとしての色々な動きがあったんです。例えば3月にワンマンツアーがあったり韓国でのライブがあったり、個人的にはでんぱ組.incというアイドルの曲を作ったりして。それを1つ1つちゃんと乗り越えていくうちに“あ、自分にはまだこんな伸びしろがあるんだ”という発見が色々とあって、更に曲ができたんですよ。“ここでまとめてしまうんじゃなくて、ギリギリまで伸びしろを増やす作業に変えた方がいいんじゃないか”と途中で思って。だから完結させるのはやめて、枝分かれしていたものを更に細かく枝分かれさせて、可能性を拡げていこうっていう感じでできた曲でアルバムを更新していったという感じ。
●なるほど。想像するに、玉屋さんはストイックに曲作りを突き詰めるタイプのソングライターだからこそ、でんぱ組.incに楽曲提供するという経験は大きかったんでしょうね。
玉屋:そうなんですよ。今までは“自分はこうじゃなきゃいけない”みたいな想いが強かったんですけど、いい意味で他人の曲だからと考えて、自分の歌ではできなかった恥ずかしいこともやってみようと。いい意味でラフに楽しく曲を作ることができたし、楽曲提供は当然のことながら期限があったので、自分なりの曲を作るコツだったり、ペースだったりとかはそこで改めて学べた気がします。それをちゃんと諦めずに乗り越えたことによって、すごく曲作りのペースも掴めたし、自分の個性みたいなものを音楽に出すことに時間が掛からなくなりました。
●ある意味、自分がわかったんですね。
玉屋:それが大きかったですね。“俺ってこういう奴だったんだ”って。案外わからないもんですよね、自分って。今までは自分に対して“こうだろう”と思っていたんですけど、意外とそれが違っていたりとかして。それを見つめ直せた分、引き出しを開ける作業というのがすごく早くなったし、どこに何が仕舞ってあるかというのが自分の中で整理できたんです。
●6/6にアルバム先行シングル『十五夜サテライト』をリリースされましたが、「十五夜サテライト」は『UTOPIA』というアルバム制作に於けるキーポイントという感じがするんですが。
玉屋:そうですね。『UTOPIA』の制作を進めている中で、「このバンドでシングルというものを出したらおもしろいよね」という話をしていたんです。その中で急にポンッと「十五夜サテライト」のアイディアが浮かんだんですよ。
●それはどういう形で?
玉屋:「十五夜サテライト」は俺の中ではファンタジーなんですけど、最初のアイディアは本当に漠然としたものだったんですよ。雰囲気とストーリーみたいなものがあって。疾走感のあるサウンドに、この曲で歌っているような日本っぽさのある切ない物語を乗せることができたら、疾走感の先にある壮大さを手に入れることができるんじゃないかなって。
●ああ〜。
玉屋:それが自分の中でピンときて、この曲をシングルで出すのはおもしろいなと。そこから急いで作ったんです。スケジュール的にはかなりタイトだったんですけど、その中でも“この曲は次のステップに進むために絶対必要だ”と思ってしっかり作った感じですね。曲の面で言えば“静”と“動”という自分たちの持っている2つの側面をやっと1つにまとめることができたし、サビでの男女ツインヴォーカルもちゃんとできたし、歌詞も今までのような単語の羅列ではなくてちゃんとした物語として、文章として伝わるようなものができたし。
●確かに今までのWiennersとはかなり違いますよね。延長線上ではあるけど、表現としては一歩二歩進んだ次元というか。
玉屋:自分が表現したかった世界観というか雰囲気を、やっとこの曲でちゃんとできたという感じですね。今までもやろうとしていたんですけど、完成までには至っていなかったというか。今回はそれをちゃんと表現しようと思ったし、ちゃんとできた。だからこれを乗り越えてすごく大きな自信になったし、このアルバムでめちゃくちゃキーになった曲です。
●この曲にも象徴されることですし、今作全体的にもそうですし、『W』からの流れでもありますけど、メロディが持つ“オリエンタル感”というのは、今作でWiennersの個性になりましたよね。
玉屋:これはもともと自分の中での癖っていうか。そういう“オリエンタル感”だったりとか、日本のお祭りのような雰囲気のあるメロディにファンタジーを感じて自然と惹かれるんですよね。今までは“これをやりすぎちゃったらあまり良くないのかな?”と思って抑えていた部分があったんですけど、でも自然に出るんだったら出しちゃえばいいやと。それがWiennersの個性になり得るものかもなって。
●うんうん。どの曲にも色々と出てますよね。
玉屋:そうですね。『W』に収録した「シャングリラ」という曲がありましたけど、あれは“まだ誰も行ったことのないどこかの国のヒットチャート第1位”を勝手に想像して作ったんですけど、今作のM-1「風流ボーイ」のメロディもそういうイメージっていうか。“オリエンタル感”というのは、自分の中では“懐かしさ”に繋がっているところがあって、「なんかこの景色見たことがあるような、ないような…初めて見るんだけどなんか懐かしい」みたいな、不思議な余韻が残る感覚というか。
●その話を聞いてすごく合点がいったんですが、今作を聴いたときにすごく歓迎すべき感情が心の中に溢れたんです。それはいろんな感情なんですけど、全部が歓迎すべきもので。でも、なせそういう感情が溢れるのか理由がよくわからなかったんですけど、それは“懐かしさ”に依るところが大きいのかもしれない。子供の頃に感じたワクワクするんだけどなんか不安みたいな感覚というか。
玉屋:そうですよね。M-12「Venus」という曲は輪廻について歌っているんですけど、イメージとしては未来にある“懐かしさ”なんですよ。未来がちょっと懐かしい感覚ということに俺はファンタジーを感じるし、現実にも感じるんです。M-7「子供の心」も同じなんですけど、子供に対する感情は“懐かしさ”もそうだし、自分が親からもらった愛情を今度は子供に渡すということは輪廻じゃないですか。なんかそういうものに惹かれるんですよね。
●なるほど。あと現時点というか今作の特徴にもなっていますが、バンドの中でのMAXさんが占める割合が、ここにきてグッと大きくなっていますね。M-4「トワイライト」はMAXさんが作詞/作曲されたとのことですが。
玉屋:前から「曲を作ればいいじゃん」と言ってたんですよ。なぜこのタイミングでMAXのパートが増えたり、具体的にフィーチャーされるようになったかというと、さっきの“伸びしろ”の話なんです。“MAXが曲を作れるようになったり、歌をメインで歌えるようになったらバンドとしての伸びしろが増えるな”と思って、1曲MAXが作詞/作曲した曲を入れようと決めたんです。
●あ、決めたんですね。
玉屋:そうです。自分が作った曲をアルバムに入れて形にするということを1回経験すれば、今後につながるだろうなと。それでMAXが「トワイライト」のメロディと曲の雰囲気を作ってきたんですけど「まだアレンジをどういう風にすればわからない」という感じだったので、「どういう風にしたいの?」と聞きながら俺がアレンジを手伝って形にしたんです。
●なるほど。
玉屋:曲を作る人間が1人よりも2人の方が幅が拡がるし、男性には作れない女性ならではの雰囲気も出るだろうし、今後俺が作った曲のアレンジをするときにも役に立つと思ったんですよ。逆にそれができないと今後行き詰るだろうから、今のうちにできるようにしたいなと思って。
●『CULT POP JAPAN』を出す直前にWiennersを知ったんですけど、そのときの印象として、MAXさんは結構控えめだなと思ったんですよ。
玉屋:そうでしたね。そもそも彼女1人だけがバンド未経験者だったんですよ。だから引け目があっただろうし、下から見上げていたというか。でも、女性というだけで武器じゃないですか。だからMAXの色を出さないのはもったいないし、いいものを持っているので引き出した方がいいなとずっと思っていたんです。
●「トワイライト」はMAXさんが人生で初めて作った曲なんですか?
玉屋:初めてです。それにしてはすごくいい曲じゃないですか(笑)。ちゃんとMAXらしさも出ているし。
●ですよね。歌詞の感性とかもすごくおもしろい。
玉屋:たぶん出し方がわからなかったというのと、自信がなかったのが大きいと思うんですけど、今は色んなものを乗り越えてきたし、今回こうやってアルバムに曲が入るし、すこしずつ自信が付いてきただろうし、自分の感性の吐き出し方も少しずつわかってきてるとは思うので、ちゃんのこのアルバムに成長できたと思います。
●『CULT POP JAPAN』の頃は、Wiennesの真ん中には玉屋さんが絶対的な存在として居る、という印象だったんですよ。良くも悪くも。
玉屋:はい。
●でも今作は、変な話ですけど“バンド”だと感じる。
玉屋:それもすごく意識しました。今でもワンマンバンド的なところはあるんですけど、昔は本当に俺が中心に居るっていう構図だったんです。でもそれは良くないと思っていたので、『W』以降はバンドの中でメンバーそれぞれが自分をどんどん出して、それぞれがこのバンドに居る意味を明確にするだとか…そういうところはすごく考えましたね。
●9月からツアーが始まるじゃないですか。今作の曲が入ることによって、ライブの印象もグッと変わると思うんですが。
玉屋:ライブも今年になって色々と試していたんです。以前は俺はステージの上手にいましたけど、今は真ん中に立つようにしたんですよ。色んな試行錯誤の末にそうなったんですけど。
●いつのタイミングでそうなったんですか?
玉屋:6月にシングル『十五夜サテライト』を出して10本くらいのツアーをまわったんですけど、そのときからですね。「こっちの方が可能性が拡がりそうだからやってみよう」って。昔、1度俺が真ん中に立ってやったライブで大コケしたんですよ。
●大コケしたというのは?
玉屋:それは俺の立ち位置がどうとかいう以前の話で、ライブ自体がクソみたいな出来だったんです。でもそれがトラウマになってしまって(笑)。でも「もう1回ちゃんとやってみよう。ダメだったらまた元に戻せばいいじゃん」って慣れないながらもやり始めたんですけど、やってみるとすごくバンドがまとまるようになったし、ライブの可能性も拡がったんです。
●それはヴォーカリストとしての自覚なんでしょうね。
玉屋:そうですね。「歌を伝えるんだったら俺は真ん中に居ないとダメだ」っていう自覚でしょうね。横に居たらある意味逃げていることにもなるし。バンドを背負って意見を言う人間がど真ん中に居た方がわかりやすいし伝わるなと思ったんです。
●なるほど。
玉屋:この立ち位置で、今のライブの感じで、『UTOPIA』の曲たちを持ってツアーをまわるということは、更にもう一段階上に行ける可能性を秘めているし、ツアーでどんどん成長できるだろうなっていう予感もあるので。だからツアーは楽しみですね。1本1本しっかりと乗り越えれば、ファイナルのワンマンでやっとひとつ完結させられるものへの足がかりを見せることができると思います。
interview:Takeshi.Yamanaka